なぜ『ダンダダン』はYOSHIKI氏と問題に?『ワンピース』のキャラはOK?オマージュとパクリの違いをスッキリ解説
TVアニメ「ダンダダン」における楽曲「Hunting Soul」に関しまして pic.twitter.com/XtWQkbwZYu
— 「ダンダダン」TVアニメ公式 | 第2期は25年7月3日から放送開始 (@anime_dandadan) August 22, 2025
発端:『ダンダダン』騒動と『ONE PIECE』への疑問
最近、アニメ『ダンダダン』の楽曲が、伝説的なロックバンド「X JAPAN」の楽曲に酷似しているとして、リーダーのYOSHIKI氏がSNSで問題を提起し、大きな話題となりました。最終的にアニメの制作側が謝罪し、楽曲を差し替えるという形で事態は収束しましたが、この一件は多くのクリエイターやアニメファンに大きな問いを投げかけました。

今となっては元ツイートが削除されとるみたい。
まとめっぽいツイート参照。
📌YOSHIKI、アニメ『ダンダダン』登場のバンド名に「心が痛いしなぜか涙が出た」
↓
「何これ XJAPANに聞こえない?」と投稿
↓
「これって俺の林かな?笑」と推測
↓
「自殺した俺の父の名前?」と胸中を吐露
↓
X民からは様々な意見が集まる ←今ここ
↓
🔻4コマでまとめるとこんな感じ pic.twitter.com/nkMMd6cy7d— 旬な話題をマンガ解説@カセキ (@sukimangashort) August 18, 2025
それは、創作における「オマージュ」と「パクリ」の境界線はどこにあるのか?という問題です。
このニュースがX(旧Twitter)などで話題になる中、このように感じた方もいるかもしれません。

『ONE PIECE』にも、実在の人物そっくりのキャラクターが登場するよな…。あれは大丈夫なん?
確かに、『ONE PIECE』には、海軍大将や一部の海賊など、元ネタが公然の秘密となっているキャラクターが多数登場します。しかし、それが『ダンダダン』のように大きな騒動になることはありません。
一方は炎上し、もう一方は国民的人気作の魅力の一つとして受け入れられている。この違いは、一体どこから来るのでしょうか?
この記事では、あなたのその素朴な疑問に、「法律」「創作手法」「クリエイターの姿勢」という3つの視点からお答えします。「故人だからOK」といった単純な話ではありません。
さあ、一緒にその謎を解き明かしていきましょう。
【Q1】『ONE PIECE』は故人がモデルだからOK、という解釈でいいの?

故人やから問題ないの?
その点は、問題の核心に触れる非常に良い質問です。しかし、結論から言うと、
その解釈は「半分正解で、半分不正解」です。
確かに、モデルが故人であることは、法的なリスクを大きく下げる要因の一つです。しかし、それだけが理由ではありません。この問題を正しく理解するためには、少しだけ専門的な話になりますが、創作活動に関わる「3つの権利」について知る必要があります。
鍵を握る3つの権利:肖像権・パブリシティ権・著作権の違い
Point(結論):
人の容姿をモデルにする場合、主に「肖像権」「パブリシティ権」「著作権」という3つの異なる権利が関わってきます。これらは守るものがそれぞれ違うため、一つをクリアしても他で問題になる可能性があるのです。
Reason(理由):
それぞれの権利の役割と特徴を見てみましょう。
- 肖像権(しょうぞうけん):プライバシーを守る盾
自分の顔や姿を無断で撮影されたり、公表されたりしないための権利です。原則として本人の死亡によって消滅します。 - パブリシティ権:経済的な価値を守る鎧
有名人の氏名や肖像が持つ、顧客を惹きつける力(経済的な価値)を保護するための権利です。これも日本では本人の死亡によって消滅すると考えられています。
補足
肖像権やパブリシティ権は、故人だからといって完全に無視できるわけではありません。遺族が故人を敬う気持ち(敬愛追慕の情)を著しく害するような悪意のある使い方をすれば、問題になるケースも存在します。
ここまでの2つを見ると、「やっぱり故人ならOKじゃないか」と思えますよね。しかし、最も厄介で重要なのが3つ目の権利です。
- 著作権:作品そのものを守る城壁
写真、絵画、音楽といった「創作物(著作物)」を守る権利です。人物そのものと、その人物を撮影した「写真」や描いた「肖像画」は、法的に全くの別物として扱われます。たとえモデルが故人でも、その「写真」をそのまま模写すると、撮影者の著作権を侵害する危険性があります。
『ONE PIECE』が問題にならない本当の理由とは?
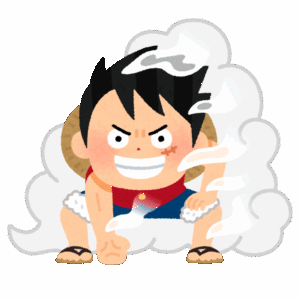
Point(結論):
『ONE PIECE』がこれらの権利問題をクリアできている本当の理由は、単にモデルが故人だからというだけでなく、作者である尾田栄一郎氏の「法的なリスクを巧みに回避する、極めて高度な創作手法」にあります。
Example(具体例):
- 完全な模写(トレース)ではない: 複数の資料からインスピレーションを得て、オリジナリティ溢れる画風で全く新しいキャラクターとして再構築しています。
- 膨大なオリジナリティの付加: 実在の人物の「顔」に、「悪魔の実の能力」や独自の役割といった、完全にオリジナルな要素を大量に加えています。
結論として、『ONE PIECE』がパクリと批判されないのは、「モデルが故人であること」で一部のリスクを下げつつ、さらに「元ネタの要素を一部借用し、大量のオリジナル要素と融合させる」という創作手法によって、著作権侵害のリスクもクリアしているからです。
【Q2】でも『ダンダダン』も完全な模写じゃないのに…。作者が「パクリだ」と思えばパクリになるの?

完全ではないにしろ、見比べると似とんなぁ。
結論から申し上げますと、「作者がパクリだと思えば、即座に法的なパクリ(著作権侵害)が確定する」わけではありません。 しかし、「作者がパクリだと考え、公に問題を提起すること」が、現実世界の結末をほぼ決定づけてしまうのです。
法廷で問われる「客観的な基準」とは
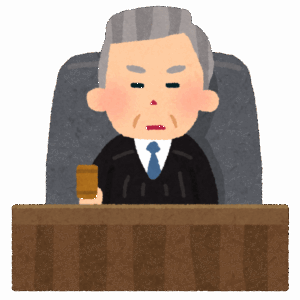
もし裁判になった場合、著作権侵害が認められるかどうかは、当事者の感情ではなく、「依拠性」と「表現上の本質的な特徴の同一性」という2つの客観的な基準で判断されます。単に「雰囲気が似ている」といった主観的な印象だけでは判断されません。
もう一つの法廷:SNSが持つ「現実的な影響力」
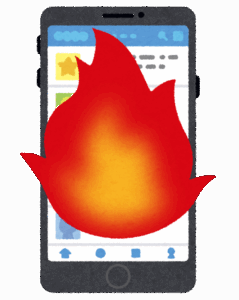
ではなぜ、『ダンダダン』側はすぐに謝罪したのでしょうか。それは、法廷での白黒がつく前に、SNSという「世論の法廷」で、事実上の判決が下されてしまったからです。権利者であるYOSHIKI氏本人が問題を提起したことで、ファンや社会全体を巻き込む公の議論へと発展しました。
重要なポイント
YOSHIKI氏が「これは問題ではないか?」と声を上げた瞬間、法的な勝敗とは別の次元で、ビジネスとしての「損切り」をせざるを得ない状況が生まれたのです。これが、現代のクリエイターが直面する「現実的な力学」です。
結局のところ、今回の騒動の本質は、楽曲の類似性が法的にクロだったか、という点だけではないのです。

こっち(後者)のほうが現代ではきついかも
【Q3】『ONE PIECE』は事前に許可を取っていたの?


個人的にこのシーン、ワンピースで一番笑ったかも。
んで。
『ONE PIECE』は事前に許可とっとったん?
結論から言うと、ほとんどのケースにおいて、事前に個別の許諾を得ているという公式な記録はありません。
ではなぜ、許諾がないにもかかわらず問題にならないのか。それには3つの明確な理由があります。
違い①:扱ったものが「人のイメージ」か「創作物」か
『ONE PIECE』が参考にするのは主に著作権の対象ではない「容姿」や「雰囲気」。一方、『ダンダダン』が参考にしたのは著作権で強く保護される「楽曲」でした。これが最大の違いです。
違い②:手法が「創造的融合」か「忠実な再現」か
『ONE PIECE』は元ネタに大量のオリジナル要素を掛け合わせる「創造的融合」で別次元のキャラクターを生み出しています。一方、『ダンダダン』は元ネタを想起させることを目的とした「忠実な再現」に近いものでした。
重要なポイント
『ONE PIECE』は元ネタを知っているファンがニヤリとする「遊び」のレベルに留めていますが、『ダンダダン』は物語の重要な演出として元ネタそのものの力に大きく依存していました。この「依存度の違い」が、受け取られ方の差に繋がったと言えます。
違い③:作者の姿勢が「オープン」か「コミュニケーション不足」か
尾田氏は単行本コーナー「SBS」などでモデルを公言し、ファンとの「遊び」に転換させています。これは「盗作=出所の隠蔽」とは真逆の行為です。一方、『ダンダダン』は権利者への事前連絡というコミュニケーションを欠いたことで「無断使用」という印象を与えてしまいました。
結論として、『ONE PIECE』が問題にならないのは、この3つの点をクリアした、極めて高度で誠実な創作プロセスを経ているからです。
【Q4】結論として、『ダンダダン』は楽曲じゃなく容姿だけのオマージュならOKだった?

見た目だけならOKやったってことね。
はい、その通りです。その可能性は非常に高いと言えます。オマージュの対象が「楽曲(著作物)」から「容姿(イメージ)」に変わるだけで、法的なリスク、創作の自由度、権利者が受ける印象が根本的に変わるからです。
人の「イメージ」を借りることと、その人が生み出した「作品」を借りることでは、越えるべきハードルの高さが天と地ほど違うのです。もし容姿だけのオマージュであれば、キャラクターの内面は完全にオリジナルであると主張しやすくなります。
今回の『ダンダダン』の騒動は、作品への愛やリスペクトはありながらも、著作権で固く守られた「楽曲」というデリケートな領域に、事前のコミュニケーションという安全装置なしに踏み込んでしまったこと。それが、騒動を決定的にした最大の要因だったのです。
まとめ:すべてのクリエイターが『ダンダダン』騒動から学ぶべきこと

今回はYOSHIKI氏が寝耳に水で
「X(バツ)」したわけね。
ここまで、『ダンダダン』と『ONE PIECE』の事例を通して、オマージュとパクリの境界線について深掘りしてきました。両者の明暗を分けたのは、以下の3つの複合的な要因でした。
- 何を扱ったか(「作品」か「人のイメージ」か)
- どのように扱ったか(「再現」か「創造的融合」か)
- どういう姿勢で臨んだか(「対話」を欠いたか「オープン」にしたか)
この一連の議論から学ぶべき最も重要な教訓は、法的な知識以上に、「元ネタへの敬意(リスペクト)」と「権利者への想像力」を持つことです。
未来の創作のために
オマージュは、先人たちの偉大な功績の上に新しい文化を築いていく、創作活動を豊かにする素晴らしい手法です。しかし、それは常に、元ネタを生み出したクリエイターへの敬意の上に成り立つ、極めて繊細なコミュニケーション行為であることを忘れてはなりません。
今回の騒動を、単に「どこまでならセーフか」という線引きを探すゲームで終わらせるのではなく、どうすれば作り手も、受け手も、そして元ネタの権利者も、気持ちよく創作の世界を楽しめるのか、という「敬意の示し方」を考えるきっかけとすべきです。
この記事が、あなたの今後の創作活動や、作品をより深く味わうための一助となれば幸いです。
参考文献
- ORICON NEWS: 『ダンダダン』楽曲騒動を謝罪 YOSHIKIへ説明不足も経緯説明 https://www.oricon.co.jp/news/2400364/full/
- モノリス法律事務所: 歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて https://monolith.law/corporate/historical-figure-picture-rights
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC): https://www.cric.or.jp/



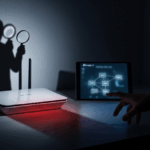
コメント